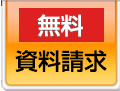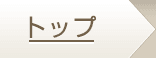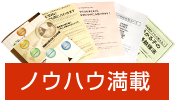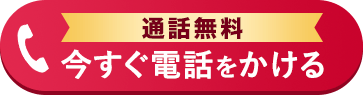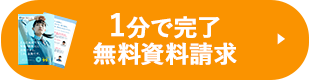大学別対策

英文学科一般入試・日本史
入試傾向と対策ポイント
家庭教師メガスタディの「津田塾大学対策ページ」にお越し頂きありがとうございます。
ここでは、私大受験のプロが「偏差値・学力が届いていなくても津田塾大学・英文学科一般入試に合格できる日本史の勉強法」を紹介します。
傾向
津田塾大学 英文学科の日本史は、大きく3つの特徴があります。
- ・問題のレベルは標準的
- ・近現代が重視される
- ・論述問題が出題される
こうした傾向に合わせ、津田塾大学 英文学科の日本史で高得点がとれる対策を、これからお伝えしていきます。
出題範囲
古代~近現代史
難易度
標準~やや難
出題量
大問4題の出題です。長文論述に時間がかかるので、この辺りの時間配分を上手くしないと、試験時間内に解き終わることができません。
出題・解答形式
ほぼ記述式で、選択式の問題はわずかです。短文論述の他、250字~300字の長文論述問題が出題されます。長文論述は、使用する語句が指定されています。
出題内容
時代別では、近現代史が重視されています。論述問題も、近現代史からの出題です。
それ以外では、近世が最も多く、年度によっては、中世や古代からの出題も見られます。
分野別では、政治史、経済史、外交史、文化史の比重が大きくなっています。
対策
教科書学習をベースにする
問題のレベルは標準的です。そのため、高得点での争いが予想され、記述問題の漢字の誤記などのケアレスミスでの失点が命取りになります。ケアレスミスをしないためには、知識を曖昧にせず、定着させることです。
そのためには、まず教科書の内容を徹底して覚えることが必要です。その際、図表脚注にもしっかり目を通し、人名、重要歴史用語などは『日本史B用語集』(山川出版)のような用語集を併用すると良いでしょう。
前後の出来事などに関連付けながら覚えることが、知識を定着させるコツです。
近現代が高得点をとるポイント
津田塾 英文学科の日本史では、近現代の比重がとくに大きいことに特徴があります。
過去には、現代史において政治や政党を問う問題も出題されています。日本史の近現代以降は、とくに覚える内容も多いので、できるだけ早い時期から、近現代の学習に取り組むことをおすすめします。学校の進捗に合わせていると、学習時間が足りなくなり、対策不十分のまま試験本番に臨むことになりかねません。
論述問題も近現代史から出題されることが多いので、とくに丁寧な学習が必要です。
ただ、前述の通り、近現代史は覚えなくてはいけない用語も多く、重要事件も頻発しており、歴史の流れや事件の相互関係を正しく掴むのは大変です。
津田塾 英文学科の傾向に詳しい人であれば、狙われやすいポイントや、覚えておくべき重要事項をよく知っているので、効率良く合格に直結した対策ができます。合格を確実にするには、こうした津田塾 英文学科の傾向に詳しい人の手を借りるのも良いでしょう。
論述
250~300字の長文論述の出来が、合否に大きく影響する可能性があります。ですから、論述対策はしっかりしておく必要があります。
論述する際には、出題者の意図を読み取り、要点を簡潔に文章化することが必要です。そのためには、論述の骨組を決めることが大切です。骨組みを決めてから論述することで、過不足のない解答を作れるようになります。
まずは、解答の骨組となる部分を箇条書きにして書き出しましょう。その箇条書きにしたものをつなぎ合わせ、文章を整えれば、要点を踏まえた解答が作れます。
使用語句指定がある場合は、その語句がヒントにもなるので、その語句を中心に文章へ発展させましょう。
外交関係や政策の推移を問う問題がよく出ているので、事実関係や前後関係の認識違いには要注意です。教科書をよく読み、時代の流れを正しく把握することが間違いのない論述を書く第一歩となります。
ただ、論述の場合、どうしても自己採点では、解答の良し悪しを正しく判断できません。必ず第三者からの添削が必要になります。このとき、津田塾 英文学科の日本史の傾向に詳しい人に添削してもらえれば、傾向に合わせて、不足しているポイントや、どう直せば解答がよくなるのかが分かります。現状の学力にも合わせ、記述力を向上させるコツを教えてくれるので、短期でも合格を可能にする解答が作れるようになります。